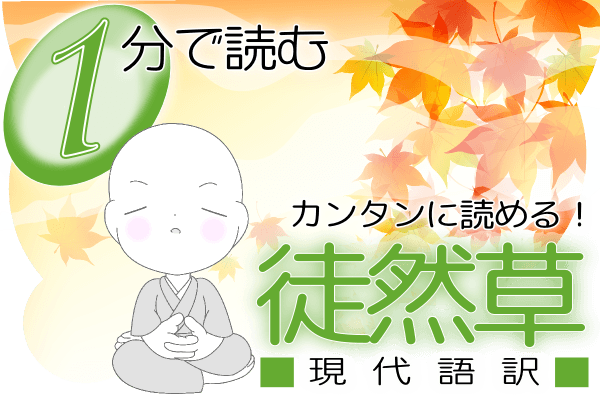徒然草・第10段
徒然草・第10段
◇家居のつきづきしくあらまほしきこそ



こんな家に住むのが理想なのだとか
理想的にできている家は、人生の仮の住まいとはいえ感心するものである。
優れた人がのんびり暮らす家は、さしこむ月の光さえしみじみするものだ。現代風でなく華やかさもなく、庭の木々は時代を経て育ち、草はいかにもわざわざ手入れしたようでない感じで、調度品も古風で落ち着いた感じなのが良い。
大工が心づくしに立派に磨きあげ、中国やら国産の珍重される調度品を並べ、庭木までも自然な姿からは程遠い細工をしてしまうのは見苦しくて心が痛むのだ。永遠に住めるわけではないのに。火事で焼け落ちたら意味がないではないかと思えてくる。おおよそ人はその住まいで推し量ることができるのである。

▲西行法師
左大臣・徳大寺実定(とくだいじさねさだ・平安時代末期の公卿)が寝殿にトンビが止まらないようにと縄を張らせていたのを西行法師(さいぎょうほうし・平安時代末期の僧侶、歌人)が見て「トンビが止まるくらい構わないじゃないか。大臣の心はその程度か」と見限って、以降は訪ねて来なかったそうである。
しかし、性恵法親王(しょうえほうしんのう・第90代亀山天皇の皇子)がお住まいに縄を張っていたので理由を尋ねてみれば、「カラスが群がり、池のカエルを捕って食べてしまうので、それをご覧になって可哀想に思われたから」だと屋敷の人が言うので、それはもっともだと感じた次第だ。徳大寺の大臣も何か理由があったのかもしれない。
 徒然草・第11段
徒然草・第11段
◇神無月のころ



中学の授業で習いましたっけか
10月頃、栗栖野(くるすの・京都市山科区)を過ぎて、ある山里を訪ねたことがあったが、遥かに続く苔の細道を歩いて行った先に寂しげに暮らしている風情の庵があった。
落ち葉に埋もれた樋から落ちる水滴の音しかしない。戸外の棚に菊や紅葉の枝が置いてあるので、誰か住んでいるのだろう。
こんなところでも生きていけるものだなとしみじみ感心していたら、庭に実がたわわに育ったミカンの木があり、盗られないように周囲を厳重に囲ってあったので、ちょっと興ざめしてしまった。この木がなかったらよかったのに。