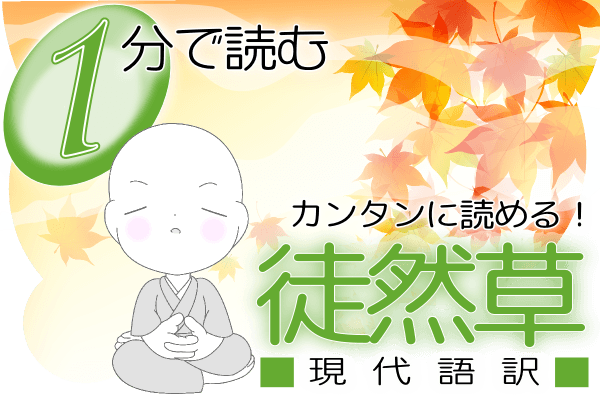徒然草・第137段
徒然草・第137段
◇花は盛りに





冒頭の文言はあまりにも有名
桜の花は満開のものだけを、月は満月だけを観て愛でるのだろうか。そうではあるまい。雨空に向かって見えない月を恋い焦がれ、簾を垂れた部屋に引き籠って、春の移ろいを知らずに過ごすのも、やはりしみじみと趣がある。
開花寸前の桜の枝や花が散り萎れた庭などは、ことに見所が多いものである。和歌の前書きにも「花見に出かけたが、早くも散ってしまったので」とか「障りがあって花見に出かけずに」とか書いてあるのは、「花見をして」と書いてあるものより劣っているだなんてことがあろうか。
花が散り、月が沈み傾くのを惜しむ風習はもっともなことではあるけれども、特に愚かな人というものは「この枝もあの枝も花が散ってしまった。もう見る価値もない」などと言うようだ。

あらゆることは、その始めと終わりこそが特に情趣があるものだ。男女の恋愛も、ただ逢って交際を深めることだけを指すものだろうか。深く交際する前に終わってしまった憂いを想ったり、叶わなかった約束を嘆き、長い夜を独りで明かし、遠くの恋人を眺める雲に想いやり、昔、逢引きした朽ち屋を思い出したりすることが、恋に浸ることなのだ。
陰りなく輝く満月を遥か遠くにまで眺め通すよりも、明け方近くになってようやく姿を見せたのが、ことさら情趣たっぷりに青みを含んで山深くの杉の枝にかかって見えていたりとか、木の間の月光や、しぐれを降らせる群れ雲に隠れた月は、またとなく趣がある。
椎の木の繁ったところや白樫の濡れた葉の上に月が煌めいている様子はまさしく身に沁みるほどに、この風情を判ってくれる友がいればと、都を恋しく思う。
おおよそ月や花は、そのように目だけで観るものだろうか。春は家から出ずとも、月夜は寝室の中からでも心のうちに花と月を思い描くことが、非常に確固として風情豊かなものなのだ。
教養ある立派な人は、花や月をやたら愛でる様子を見せたりはしないし、愛でる姿も淡白なものだ。片田舎から上京したような人が、なんでもしつこく持て囃すのだ。
桜の木の下に身をねじるように立ち寄り、脇目も振らずじっと見つめ、酒を飲んで、連歌をして、挙句には大きな枝を心無く折ってしまう。湧き出る泉に手足を浸したり、新雪に下りて足跡をつけたりなど、なんでもかんでも遠くから眺めて楽しむと言うことをしないのである。

そういう人が祭りを見物する姿は、まことに異様だった。
「行列が来るのが遅いから、それまで見物席にいても無駄」
とか言って、奥で酒を飲んで物を食べて、囲碁やスゴロクで遊んで、見物席には見張りを置いておく。
見張りが「行列が来ました」と言うと、おのおのがビックリした様子で先を争って見物席に走り上り、転げ落ちてしまいそうになるまで簾を押し広げて押し合いへし合い、一切を見落とすまいと目を凝らして「ああだこうだ」といちいち言って、行列が通り過ぎてしまうと「また次の行列が来るまで」と言って下りてしまう。彼らはただ単に行列を見ようとしているだけなのだ。
都の人で立派な人物なら、眠ったままで大してよく見もしない。若い末席の者は上役への奉仕に立ち振舞っているし、貴人の後ろに控える者は不格好にも前の人にのしかかったり無理やり行列を見ようとすることもない。
祭りの初日は、場所取りの葵の葉を良い位置に何となしに懸け渡しておく。夜が明けないうちにそっと牛車を寄せておくので、その牛車は誰が乗るのだろうか、あの人かこの人かと考えてしまう。中には牛飼いや下僕に顔見知りがいることがある。
風情たっぷりに煌びやかに飾り立てた牛車が行き交うのを眺めるのも退屈しなくてよい。
日暮れには立ち並んでいた牛車たちも、立錐の余地がないほどに居た人たちもどこへ消えてしまったのだろう。だんだん数少なくなっていって、行き交う牛車のけたたましさも掻き失せてしまうと、見物席の簾や畳も取り去られ、眼前がさびしげになっていく。これぞ栄枯必衰の世の習いを思われて風趣がある。行列の通る大通りの有り様を見ることが、実は祭りを見ることなのだ。

あの見物席の前を大勢行き交う人たちの中に、顔見知りがたくさんいる。これにて世の中の人の数もそれほど多くはないのだと悟る。これらの人たちが皆死んでしまった後に自分も死ぬのだと決まっているにせよ、ほどなくしてその時が来ることは間違いない。
大きな器に水を入れて小さな穴をあけた時、滴り落ちる水はごくわずかだと言っても、絶え間なく滴ればそのうち中の水は尽きてしまう。同様に、都にたくさんいる人たちが全く死なない日などない。一日に一人か二人だけということがあろうか。鳥部野(とりべの・京都市東山区の火葬場、墓地)や舟岡(ふなおか・京都市上京区の火葬場、墓地)、そのほかの野山の墓地にも亡き人を送る数が多い日はあっても、まったくない日などないのである。
なので棺桶を売る者は、棺桶を製造してそのまま置いておく暇もない。
若かろうが強靭であろうが、思いがけずやって来るものは死である。今日まで死を免れて来れたことこそ、珍しくも不思議なことなのだ。わずかな時間でもこの世が永遠に続くようだと思っていて良いものだろうか。

継子立て(ままこだて・人を環状に並べ、いくつか決まった数にいる者を順に抜き出し、残った者を決める遊び)をスゴロクで使う石で環を作って並べている間は、どの石が取られるのかまだ判らない。そして数を決めてひとつの石を取り去れば、他の石は取り去られるのを免れたかのように見える。しかし、次々と数を決めて、あれもこれもと取り去って行けば、結局どの石も逃れられないのと似ている。
兵が戦に出るとき、死の接近を知り、家のことを忘れ、自身のことも忘れるのである。俗世に背を向けた草庵で、のんびりと自然にたわむれ、死の到来を自分に無関係なことだと思って聞いているようではなんとも頼りない。静かな山奥に無常という名の死の敵が、勇んでやって来ないことがあろうか。草庵で死に臨んでいることとは、つまり、兵が戦地に出るのと同じことなのである。