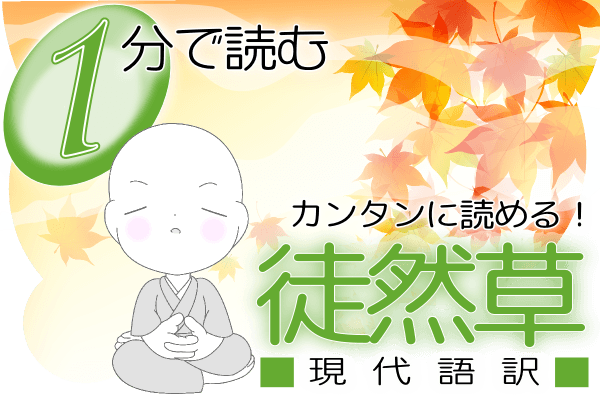徒然草・第30段
徒然草・第30段
◇人の亡き跡ばかり悲しきはなし



人の生きざまも後年には風化するもの
人が死んだ後ほど悲しいものはない。
四十九日の間は不便な山里に移り、狭い場所に大勢が集って仏事を執り行うこと慌ただしい。日が過ぎ行く速さはこれ以上のものはないと思えるほどだ。四十九日には皆好き勝手に去っていってしまう。
家に戻ったところで、より悲しみは多い。そんなときに「これはこうで、ああで、縁起が悪いから避けねば」と言ってのけるのは、こんな折に何てことをと人の心を情けなく感じる。
年月が流れても忘れはしないが「去る者日々に疎し」と言うように、亡くなったときほどには悲しみを感じず、故人のよもやま話をしては笑い合うものだ。

亡骸は山に埋葬し命日などに参ってみれば、ほどなくして卒塔婆には苔が生え、落ち葉が積もり、夕刻の嵐や夜の月だけが話しかけてくれる者となっている。
思い出しては偲んでくれる人がいるうちはいいが、その人も死んで、名前のみ伝わっている程度しかない子孫が果たして哀れに思ってくれようか。
そして法事もしなくなり、名前すら知られず、情緒を解する人が墓に生える春の草ばかりをしみじみ見入ることはあれど、墓のそばにあった松の古木も切り倒されて薪になり、墓の土も掘り返されて田んぼになってしまうのである。
亡き人の墓のあとかたすらなくなってしまうのは悲しいものだ。
 徒然草・第31段
徒然草・第31段
◇雪のおもしろう降りたりし朝


兼好の周りにはやはり兼好に似た友人がいたのだなと納得
雪が風情たっぷりに降った朝、ある人へ伝えねばならぬことがあり手紙を遣わせたのだが、雪のことには触れずに送ったところ、返信で
「この雪をどう見たのかと、ひとこと触れもしないようなひねくれ者の言うことは聞けません。ああ情けない」と書いてあったのはおもしろかった。
今はもう亡き人なので、この程度のことですら忘れがたい。