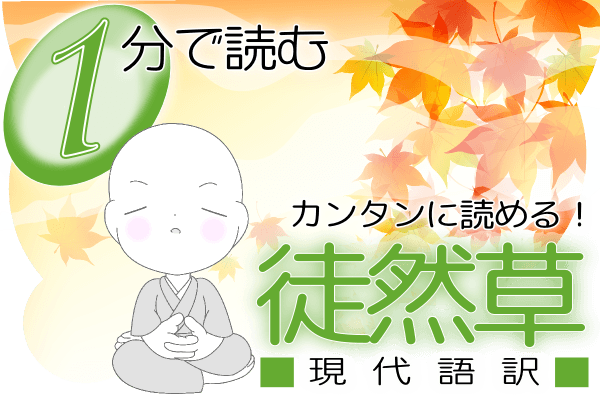
徒然草は意外と面白い!
笑い話から人生観まで簡単読破
 徒然草って何だろう?
徒然草って何だろう?
徒然草(つれづれぐさ)は鎌倉時代末期、1330年代あたりに成立したとされるエッセイ。日本三大随筆のひとつ。作者は卜部兼好(うらべけんこう・吉田兼好)。京都・吉田神社の神職の子として生まれた歌人、古典学者、能書家 。
全243段の内容は世俗への辛辣な批判からユーモア、死生観にいたるまでさまざまあり、多様。
 もくじ
もくじ
 上巻
上巻
 序段◇つれづれなるままに
序段◇つれづれなるままに

誰もが知っている書きだしの一節 第1段◇いでやこの世に生れては
第1段◇いでやこの世に生れては


このように生きていきたいものだという理想 第2段◇いにしへのひじりの御代の
第2段◇いにしへのひじりの御代の


質実こそすばらしい 第3段◇万にいみじくとも
第3段◇万にいみじくとも


吉田兼好の恋愛論 第4段◇後の世の事心に忘れず
第4段◇後の世の事心に忘れず
一瞬で読み終わります 第5段◇不幸に憂に沈める人の
第5段◇不幸に憂に沈める人の



吉田兼好らしい思考回路?
 第6段◇わが身のやんごとなからんにも
第6段◇わが身のやんごとなからんにも



子供は作らない方がいいそうです 第7段◇あだし野の露消ゆる時なく
第7段◇あだし野の露消ゆる時なく



40歳までに死ねと説きつつ、自身は70歳近くまで生きていたという矛盾 第8段◇世の人の心惑はす事
第8段◇世の人の心惑はす事


吉田兼好ですらエロには勝てず 第9段◇女は髪のめでたからんこそ
第9段◇女は髪のめでたからんこそ

そんな兼好の女性対策? 第10段◇家居のつきづきしくあらまほしきこそ
第10段◇家居のつきづきしくあらまほしきこそ



こんな家に住むのが理想なのだとか
 第11段◇神無月のころ
第11段◇神無月のころ



中学の授業で習いましたっけか 第12段◇同じ心ならん人としめやかに物語して
第12段◇同じ心ならん人としめやかに物語して

結局、真の友は得難いものなのです 第13段◇ひとり燈のもとに文をひろげて
第13段◇ひとり燈のもとに文をひろげて
吉田兼好お薦めの書物 第14段◇和歌こそなほをかしきものなれ
第14段◇和歌こそなほをかしきものなれ



懐古主義は当時から健在 第15段◇いづくにもあれしばし旅立ちたるこそ
第15段◇いづくにもあれしばし旅立ちたるこそ

旅は良いものですよね
 第16段◇神楽こそなまめかしく
第16段◇神楽こそなまめかしく
一瞬で読破できます 第17段◇山寺にかきこもりて
第17段◇山寺にかきこもりて
これも一瞬で読破できます 第18段◇人は己れをつづまやかにし
第18段◇人は己れをつづまやかにし



ここまで徹底すれば確かに清々しい 第19段◇折節の移り変るこそ
第19段◇折節の移り変るこそ


「春はあけぼの」の徒然草版 第20段◇某とかやいひし世捨人の
第20段◇某とかやいひし世捨人の

短くも深い内容
 第21段◇万のことは月見るにこそ
第21段◇万のことは月見るにこそ



自然と触れ合えば心が晴れるのは今も昔も同じです 第22段◇何事も古き世のみぞ慕はしき
第22段◇何事も古き世のみぞ慕はしき


特に言葉遣いについて懐古主義が炸裂します 第23段◇衰へたる末の世とはいへど
第23段◇衰へたる末の世とはいへど


天皇が住まう内裏についての兼好の見解 第24段◇斎宮の野宮におはしますありさまこそ
第24段◇斎宮の野宮におはしますありさまこそ

神社もまた素晴らしいのです 第25段◇飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば
第25段◇飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば



書き出しがなんとも方丈記そっくり?
 第26段◇風も吹きあへずうつろふ
第26段◇風も吹きあへずうつろふ

男女の別れは兼好だって悲しいんです 第27段◇御国譲りの節会行はれて
第27段◇御国譲りの節会行はれて

人の心の頼りなさはこんなときにも露見します 第28段◇諒闇の年ばかり
第28段◇諒闇の年ばかり

一瞬で読めます 第29段◇静かに思へば万に
第29段◇静かに思へば万に

過去を懐かしく思う気持ちは誰も同じ 第30段◇人の亡き跡ばかり悲しきはなし
第30段◇人の亡き跡ばかり悲しきはなし



人の生きざまも後年には風化するもの
 第31段◇雪のおもしろう降りたりし朝
第31段◇雪のおもしろう降りたりし朝


兼好の周りにはやはり兼好に似た友人がいたのだなと納得 第32段◇九月廿日の比
第32段◇九月廿日の比


ちょっとしたことで人の価値って判ったりするものです 第33段◇今の内裏作り出されて
第33段◇今の内裏作り出されて


昔の細かいことに詳しい人は重宝されるもの 第34段◇甲香はほら貝のやうなるが
第34段◇甲香はほら貝のやうなるが
方言って独特 第35段◇手のわろき人の
第35段◇手のわろき人の


手癖が悪い人、という意味ではありません
 第36段◇久しくおとづれぬ比
第36段◇久しくおとづれぬ比

女性の気遣いについて 第37段◇朝夕隔てなく馴れたる人の
第37段◇朝夕隔てなく馴れたる人の


友人を見直すふとした瞬間の話 第38段◇名利に使はれて
第38段◇名利に使はれて


人に不要なモノとは何か 第39段◇或人法然上人に
第39段◇或人法然上人に


賢人の返答の妙 第40段◇因幡国に何の入道とかやいふ者の娘
第40段◇因幡国に何の入道とかやいふ者の娘


あっさりした書きかたが、また可笑しさを誘います
 第41段◇五月五日賀茂の競べ馬を見侍りしに
第41段◇五月五日賀茂の競べ馬を見侍りしに


結果的に自慢話になっている気が 第42段◇唐橋中将といふ人の子に
第42段◇唐橋中将といふ人の子に

世にも奇妙な病の話 第43段◇春の暮つかた
第43段◇春の暮つかた

一歩間違えたらストーカーです 第44段◇あやしの竹の編戸の内より
第44段◇あやしの竹の編戸の内より

これも一歩間違えたら… 第45段◇公世の二位のせうとに良覚僧正と聞えしは
第45段◇公世の二位のせうとに良覚僧正と聞えしは



その昔、「まんが日本昔ばなし」でも放送されたエピソード
 第46段◇柳原の辺に
第46段◇柳原の辺に


第45段を受けての超ショートショート 第47段◇或人清水へ参りけるに
第47段◇或人清水へ参りけるに


傍から見たらただの変人です 第48段◇光親卿院の最勝講奉行してさぶらひけるを
第48段◇光親卿院の最勝講奉行してさぶらひけるを

常識も時代が変われば変化するということです 第49段◇老来たりて始めて道を行ぜんと
第49段◇老来たりて始めて道を行ぜんと




要は今すぐ出家しろという話 第50段◇応長の比伊勢国より
第50段◇応長の比伊勢国より



いかに人間がデマに騙されやすいかという話
