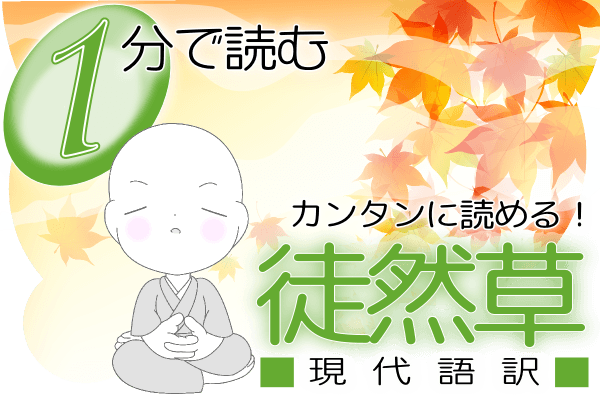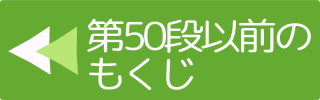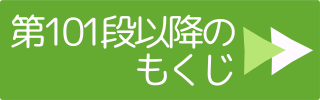もくじ
もくじ
 上巻
上巻
 第51段◇亀山殿の御池に
第51段◇亀山殿の御池に

餅は餅屋ですね 第52段◇仁和寺にある法師
第52段◇仁和寺にある法師




中学校で習いましたよね 第53段◇これも仁和寺の法師
第53段◇これも仁和寺の法師




仁和寺はネタの宝庫なのでしょうか 第54段◇御室にいみじき児のありけるを
第54段◇御室にいみじき児のありけるを




まさかの仁和寺第3弾! 第55段◇家の作りやうは
第55段◇家の作りやうは


これもまた有名な段。兼好も夏の暑さは苦手だったようで
 第56段◇久しく隔りて逢ひたる人の
第56段◇久しく隔りて逢ひたる人の

どの時代でもお喋りな人は良く思われないようです 第57段◇人の語り出でたる歌物語の
第57段◇人の語り出でたる歌物語の

知ったかぶりは呆れられます 第58段◇道心あらば住む所にしもよらじ
第58段◇道心あらば住む所にしもよらじ

とにかく出家しろと言いたいような 第59段◇大事を思ひ立たん人は
第59段◇大事を思ひ立たん人は

とにかく今すぐ出家しろと言いたいような 第60段◇真乗院に盛親僧都とて
第60段◇真乗院に盛親僧都とて



仁和寺の法師第4弾!!!!
 第61段◇御産の時甑落す事は
第61段◇御産の時甑落す事は

こんな風習があったのですね 第62段◇延政門院いときなくおはしましける時
第62段◇延政門院いときなくおはしましける時


ちょっぴり暗号のような和歌 第63段◇後七日の阿闍梨武者を集むる事
第63段◇後七日の阿闍梨武者を集むる事

内裏の仏事における風習 第64段◇車の五緒は
第64段◇車の五緒は
鎌倉時代の車のステイタス 第65段◇この比の冠は
第65段◇この比の冠は
鎌倉時代のフォーマルファッションにも流行が
 第66段◇岡本関白殿盛りなる紅梅の枝に
第66段◇岡本関白殿盛りなる紅梅の枝に


その道のプロには素人にはわからない流儀があるってこと 第67段◇賀茂の岩本橋本は
第67段◇賀茂の岩本橋本は


上賀茂神社の末社のおはなし 第68段◇筑紫になにがしの押領使などいふやうなる
第68段◇筑紫になにがしの押領使などいふやうなる


「鶴の恩返し」ならぬ「大根の恩返し」? 第69段◇書写の上人は
第69段◇書写の上人は



豆がしゃべった! 第70段◇元応の清暑堂の御遊に
第70段◇元応の清暑堂の御遊に

トラブルがあっても機転を利かせて回避
 第71段◇名を聞くよりやがて面影は
第71段◇名を聞くよりやがて面影は

デジャブってありますよね 第72段◇賤しげなる物
第72段◇賤しげなる物


枕草子の「ものづくし」です 第73段◇世に語り伝ふる事
第73段◇世に語り伝ふる事

この世にはびこる嘘とどう付き合うか 第74段◇蟻の如くに集まりて
第74段◇蟻の如くに集まりて


どうせすぐ死ぬんだから、というのが結論 第75段◇つれづれわぶる人は
第75段◇つれづれわぶる人は


第74段を受けて、ではどう生きるべきかという話
 第76段◇世の覚え花やかなるあたりに
第76段◇世の覚え花やかなるあたりに

坊主は世俗にまみれるな、ということです 第77段◇世中にその比
第77段◇世中にその比

地獄耳でおしゃべりな人は自覚がないようです 第78段◇今様の事どもの珍しきを言い広め
第78段◇今様の事どもの珍しきを言い広め


これは普段から気を付けておきたい 第79段◇何事も入りたたぬさましたるぞよき
第79段◇何事も入りたたぬさましたるぞよき

要はべらべらしゃべるなということ 第80段◇人ごとに我が身にうとき事をのみぞ
第80段◇人ごとに我が身にうとき事をのみぞ



コレ、武道家が読んだら怒りますよ
 第81段◇屏風障子などの絵も文字も
第81段◇屏風障子などの絵も文字も


家具や道具のチョイスのしかた 第82段◇羅の表紙は疾く損ずるがわびしき
第82段◇羅の表紙は疾く損ずるがわびしき



不完全の美学 第83段◇竹林院入道左大臣殿太政大臣に上り給はんに
第83段◇竹林院入道左大臣殿太政大臣に上り給はんに

これもいわば不完全の美学 第84段◇法顕三蔵の天竺に渡りて
第84段◇法顕三蔵の天竺に渡りて


強いて言えばこれも不完全の美学 第85段◇人の心すなほならねば
第85段◇人の心すなほならねば



ある意味毒舌入ってます
 第86段◇惟継中納言は
第86段◇惟継中納言は

徒然草にはあだ名のネタがいくつもあります 第87段◇下部に酒飲ますることは
第87段◇下部に酒飲ますることは


史上最低の酔っ払いの話 第88段◇或者小野道風の書ける和漢朗詠集とて
第88段◇或者小野道風の書ける和漢朗詠集とて


ニセモノほど価値がある!? 第89段◇奥山に猫またといふものありて
第89段◇奥山に猫またといふものありて


あっさりと書き記したオチが秀逸 第90段◇大納言法印の召使ひし乙鶴丸
第90段◇大納言法印の召使ひし乙鶴丸

妻の浮気を問い詰める夫 お寺ver.
 第91段◇赤舌日といふ事
第91段◇赤舌日といふ事



日取りの縁起にこだわることのバカバカしさ 第92段◇或人弓射る事を習ふに
第92段◇或人弓射る事を習ふに

今この瞬間を懸命に 第93段◇牛を売る者あり
第93段◇牛を売る者あり


ちょっと強引な論理展開ですが… 第94段◇常磐井相国出仕し給ひけるに
第94段◇常磐井相国出仕し給ひけるに

こんなあっさり解雇されるのもある意味ひどい 第95段◇箱のくりかたに緒を付くる事
第95段◇箱のくりかたに緒を付くる事
細かいことにもいろいろしきたりやら何やらがあるもの
 第96段◇めなもみといふ草あり
第96段◇めなもみといふ草あり
あんまり役に立ちそうにもない豆知識。むしろ実践してはダメ 第97段◇その物に付きてその物をつひやし損ふ物
第97段◇その物に付きてその物をつひやし損ふ物


一瞬自己否定かと錯覚するような毒舌短文 第98段◇尊きひじりの言ひ置きける事を書き付けて
第98段◇尊きひじりの言ひ置きける事を書き付けて

しょっぱな、それでいいのか?と思わせる名言 第99段◇堀川相国は美男のたのしき人にて
第99段◇堀川相国は美男のたのしき人にて

古い物ってすばらしい 第100段◇久我相国は殿上にて水を召しけるに
第100段◇久我相国は殿上にて水を召しけるに
100番目の段は短いうえに大した内容がない