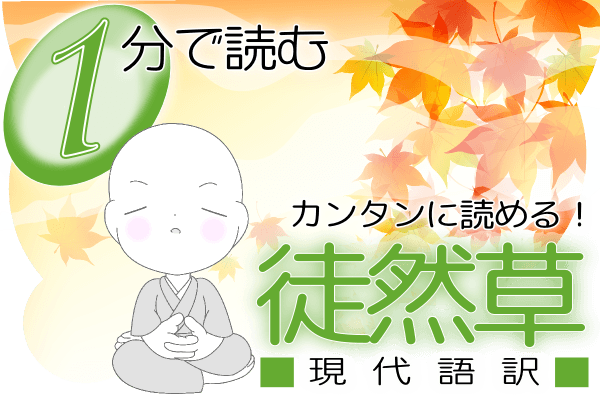もくじ
もくじ
 下巻
下巻
 第181段◇降れ降れ粉雪たんばの粉雪といふ事
第181段◇降れ降れ粉雪たんばの粉雪といふ事


童謡のフレーズも奥が深いものです
 第182段◇四条大納言隆親卿乾鮭と言ふものを
第182段◇四条大納言隆親卿乾鮭と言ふものを

確かに鮭とばも上品というイメージはありませんが
 第183段◇人觝く牛をば角を截り
第183段◇人觝く牛をば角を截り

養老律令の雑令の記述
 第184段◇相模守時頼の母は
第184段◇相模守時頼の母は


昭和期の国語教科書などにも取り上げられた話
 第185段◇城陸奥守泰盛は
第185段◇城陸奥守泰盛は


その道のプロの心構え
 第186段◇吉田と申す馬乗りの申し侍りしは
第186段◇吉田と申す馬乗りの申し侍りしは

引き続いて馬術の心得の話
 第187段◇万の道の人
第187段◇万の道の人


プロとアマの違い
 第188段◇或者、子を法師になして
第188段◇或者、子を法師になして



すぐやるべきことは何かを見極めることの大切さ
 第189段◇今日はその事をなさんと思へど
第189段◇今日はその事をなさんと思へど



要は、なるようになるんです。
 第190段◇妻といふものこそ
第190段◇妻といふものこそ


これは現代なら非難の嵐になりそう
 第191段◇夜に入りて物の映えなしといふ人
第191段◇夜に入りて物の映えなしといふ人


ほの暗いバーを好むような感覚
 第192段◇神仏にも人の詣でぬ日
第192段◇神仏にも人の詣でぬ日

第191段を受けてのシンプルな段
 第193段◇くらき人の
第193段◇くらき人の


専門家を侮るべからず
 第194段◇達人の人を見る眼は
第194段◇達人の人を見る眼は


嘘に対する人のふるまい十人十色
 第195段◇或人、久我縄手を通りけるに
第195段◇或人、久我縄手を通りけるに


貴人も認知症になるのです
 第196段◇東大寺の神輿
第196段◇東大寺の神輿


第195段の貴人がまだ元気だったころの逸話 第197段◇諸寺の僧のみにもあらず
第197段◇諸寺の僧のみにもあらず

へ、へえ・・そうなんだ・・としか 第198段◇揚名介に限らず
第198段◇揚名介に限らず

これも、あ・・そうなのね・・としか 第199段◇横川行宣法印が申し侍りしは
第199段◇横川行宣法印が申し侍りしは
音楽について兼好が述べるのは珍しい 第200段◇呉竹は葉細く
第200段◇呉竹は葉細く

これまた使い道のないマメ知識
 第201段◇退凡下乗の卒塔婆
第201段◇退凡下乗の卒塔婆
同じくどうでもいいマメ知識 第202段◇十月を神無月と言ひて
第202段◇十月を神無月と言ひて

現在では神々が出雲大社に集うから、といいますが 第203段◇勅勘の所に靫懸くる作法
第203段◇勅勘の所に靫懸くる作法

ここに犯罪者がいますよー!という目印…? 第204段◇犯人を笞にて打つ時は
第204段◇犯人を笞にて打つ時は
拷問豆知識 第205段◇比叡山に大師勧請の起請といふ事は
第205段◇比叡山に大師勧請の起請といふ事は

契約書なんて要らない!?
 第206段◇徳大寺故大臣殿、検非違使の別当の時
第206段◇徳大寺故大臣殿、検非違使の別当の時



変に気にするからおかしなことになる、という話 第207段◇亀山殿建てられんとて
第207段◇亀山殿建てられんとて


迷信を真に受けない科学的(?)考え 第208段◇経文などの紐を結ふに
第208段◇経文などの紐を結ふに



シンプル・イズ・ベスト 第209段◇人の田を論ずる者
第209段◇人の田を論ずる者


滑稽な悪人の論理 第210段◇喚子鳥は春のものなりとばかり言ひて
第210段◇喚子鳥は春のものなりとばかり言ひて

喚子鳥はカッコウ、鵺はトラツグミのこと
 第211段◇万の事は頼むべからず
第211段◇万の事は頼むべからず


何かをアテにして生きてはいけないと説く 第212段◇秋の月は
第212段◇秋の月は


兼好も愛した中秋の名月 第213段◇御前の火炉に火を置く時は
第213段◇御前の火炉に火を置く時は

こんなことにも作法が! 第214段◇想夫恋といふ楽は
第214段◇想夫恋といふ楽は

雅楽の曲の意外な由来 第215段◇平宣時朝臣、老の後
第215段◇平宣時朝臣、老の後


質素倹約を善しとした権力者の逸話
 第216段◇最明寺入道、鶴岡の社参の次に
第216段◇最明寺入道、鶴岡の社参の次に

用意周到すぎるおもてなし 第217段◇或大福長者の云はく
第217段◇或大福長者の云はく

金持ちの意見と兼好の意見、どちらを聞き入れますか? 第218段◇狐は人に食ひつくものなり
第218段◇狐は人に食ひつくものなり


兼好が記すキツネの生態 第219段◇四条黄門命ぜられて云はく
第219段◇四条黄門命ぜられて云はく

真の名人は道具を選ばない