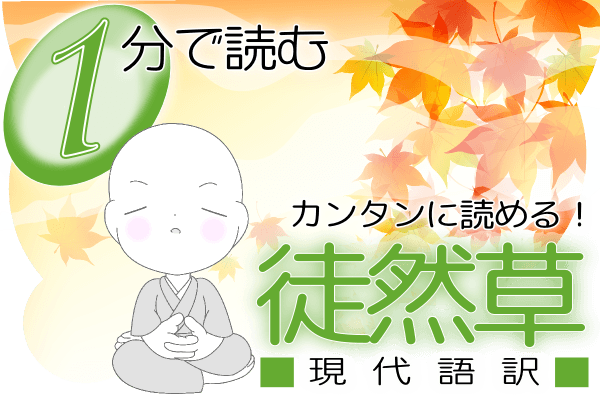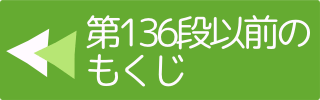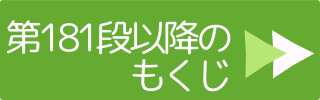もくじ
もくじ
 下巻
下巻
 第137段◇花は盛りに
第137段◇花は盛りに





冒頭の文言はあまりにも有名 第138段◇祭過ぎぬれば
第138段◇祭過ぎぬれば


祭りの後で飾りを撤去するのはダメという、意義がよく分からない主張 第139段◇家にありたき木は
第139段◇家にありたき木は



枕草子の「木の花は」と読み比べてみては? 第140段◇身死して財残る事は
第140段◇身死して財残る事は


持たざる生活はなかなか難しいものです 第141段◇悲田院尭蓮上人は
第141段◇悲田院尭蓮上人は

関東人vs関西人はこのころからあったようで 第142段◇心なしと見ゆる者も
第142段◇心なしと見ゆる者も


兼好が語る政治論 第143段◇人の終焉の有様のいみじかりし事など
第143段◇人の終焉の有様のいみじかりし事など

人の死をああだこうだ言わないのが一番かも 第144段◇栂尾の上人道を過ぎ給ひけるに
第144段◇栂尾の上人道を過ぎ給ひけるに



ダジャレ小噺 第145段◇御随身秦重躬、北面の下野入道信願を
第145段◇御随身秦重躬、北面の下野入道信願を

あいつはいつかしでかす、と思っていたら現実になったという話
 第146段◇明雲座主相者にあひ給ひて
第146段◇明雲座主相者にあひ給ひて

占いというモノはこういうことなのかもしれない 第147段◇灸治あまた所になりぬれば
第147段◇灸治あまた所になりぬれば
何故そんな迷信ができたのでしょう…? 第148段◇四十以後の人
第148段◇四十以後の人
奥の細道の松尾芭蕉も旅の始めにこのツボに灸を据えました 第149段◇鹿茸を鼻に当てて嗅ぐべからず
第149段◇鹿茸を鼻に当てて嗅ぐべからず
鹿の新しく生えた角は強壮剤に使うのだとか 第150段◇能をつかんとする人
第150段◇能をつかんとする人

ワザを磨くには名人の下で切磋琢磨せよとの話
 第151段◇或人の云はく、年五十になるまで
第151段◇或人の云はく、年五十になるまで

当時の平均寿命を考えると、現代では80歳くらいの感覚でしょうか 第152段◇西大寺静然上人、腰屈まり
第152段◇西大寺静然上人、腰屈まり



徒然草といえばこの人、日野資朝! 第153段◇為兼大納言入道召し捕られて
第153段◇為兼大納言入道召し捕られて



日野資朝シリーズ第2弾! 第154段◇この人、東寺の門に雨宿りせられたりけるに
第154段◇この人、東寺の門に雨宿りせられたりけるに


日野資朝シリーズ第3弾! 第155段◇世に従はん人は
第155段◇世に従はん人は



死は背後から迫りくる
 第156段◇大臣の大饗は
第156段◇大臣の大饗は

当時にはいろんな風習があるようで 第157段◇筆を取れば物書かれ
第157段◇筆を取れば物書かれ


何かをするのに形から入るというのはひとつの真理 第158段◇盃の底を捨つる事は
第158段◇盃の底を捨つる事は

言葉の由来シリーズその1 第159段◇みな結びと言ふは
第159段◇みな結びと言ふは

言葉の由来シリーズその2 第160段◇門に額懸くるを
第160段◇門に額懸くるを


言葉は時代で変化していくものですから
 第161段◇花の盛りは
第161段◇花の盛りは

使えそうであまり使い道のない豆知識 第162段◇遍照寺の承仕法師
第162段◇遍照寺の承仕法師


徒然草に出て来る坊主はちょっとおかしいのが多い 第163段◇太衝の太の字
第163段◇太衝の太の字

太宰府と大宰府、太平洋と大西洋 第164段◇世の人相逢ふ時
第164段◇世の人相逢ふ時


潤いのない生活の推奨?! 第165段◇吾妻の人の都の人に交り
第165段◇吾妻の人の都の人に交り

吾妻の人の都の人に交り
 第166段◇人間の営み合へるわざを見るに
第166段◇人間の営み合へるわざを見るに


努力は無駄!という話ではありませんが 第167段◇一道に携はる人
第167段◇一道に携はる人


吉田兼好流の自慢話の戒め 第168段◇年老いたる人の
第168段◇年老いたる人の


吉田兼好流の自慢話の戒め・年寄り編 第169段◇何事の式といふ事は
第169段◇何事の式といふ事は

そんなことは本人に言いなさいよと思ってしまいますが 第170段◇さしたる事なくて人のがり行くは
第170段◇さしたる事なくて人のがり行くは

自分がするのはイヤだけど、されると嬉しいそうです
 第171段◇貝を覆ふ人の
第171段◇貝を覆ふ人の


拡大路線はいつか躓くものです 第172段◇若き時は
第172段◇若き時は


今どきの老人には当てはまらないようですけれど… 第173段◇小野小町が事
第173段◇小野小町が事

謎多き女性・小野小町 第174段◇小鷹によき犬、大鷹に使ひぬれば
第174段◇小鷹によき犬、大鷹に使ひぬれば

要は出家しろってこと 第175段◇世には心得ぬ事の多きなり
第175段◇世には心得ぬ事の多きなり


酒は綺麗に飲みたいものです
 第176段◇黒戸は
第176段◇黒戸は

どんなものの名前にも由来があるものです 第177段◇鎌倉中書王にて御鞠ありけるに
第177段◇鎌倉中書王にて御鞠ありけるに

咄嗟の機転が失敗になった一例 第178段◇或所の侍ども
第178段◇或所の侍ども

そっと教えるところが奥ゆかしいのでしょう 第179段◇入宋の沙門道眼上人
第179段◇入宋の沙門道眼上人

いろんなことにこだわって探求する人がいるもので 第180段◇さぎちやうは
第180段◇さぎちやうは
日本にもホッケーがあった